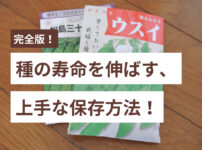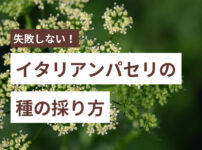「ナスの種ってどうやって採るの?」「家庭菜園でもできる?」そんな疑問にお答えします! この記事では、ナスの特徴と、実際に家庭菜園で育てて種採りする方法を、初心者にもわかりやすくご紹介します。
ナスの種採りはプランターでも地植えでも可能で、コツさえつかめば意外と簡単にできます。完熟させたナスから丁寧に種を取り出し、しっかり乾燥・保存すれば、翌年の家庭菜園がさらに楽しくなるはずです。
ナスの種採り概要
- 自家採種の時期:9月中旬〜下旬ごろ(第2果の肥大が止まったころ)
- 採種方法:完熟させてから果肉を揉み、種子を洗浄・乾燥
- 1株からの採種量:かなり多め、家庭菜園で来年使うには十分な量(採種果1〜2果でも500粒)
- 種採りに向く品種:泉州水ナス、黒十全、真黒ナス、久留米長ナス、仙台長ナス、早生真黒、橘田中長ナス、民田ナス、小布施丸ナス、山科ナス、在来青ナス、埼玉青大丸ナス、山本ナス、ヴィオレッタ・デ・フィレンツェ、越後白ナス、立石中長ナスなど(いずれも固定種)
ナスの種採りのポイント
ナスで良い種を採るためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
1. 完熟した実を選ぶ
ナスは着果から最低でも40日以上、理想は約55〜60日間木につけたままにしておくことで、種がしっかりと発芽力を持ちます。収穫時には紫の光沢がなくなり、黄褐色になっているのが目安です。果肉が柔らかく、押すと変形するくらいが収穫適期です。
収穫のタイミングは地域の気温に合わせて調整しましょう。例えば、寒冷地では8月初旬、温暖地では8月中旬に採種果を着果させておくのが理想です。これは、平均気温が17℃を下回る前に熟させるためです。
麻ひもやピンクの毛糸などで印をつけたナスを目印にしておくと、どれが採種果かが分かりやすく便利です。
特に丸ナスや米ナス系は交雑しやすいため、距離や配置に注意して隔離栽培する必要があります。
収穫後は腐りや傷みがなければ、室内で10〜14日間ほど追熟させます。果実内の養分がしっかり種に行き渡るようにしましょう。腐敗に注意しながら、適度に様子を見て管理します。
ナスの皮が硬く分厚くなり、中身が乾燥してきた頃が完熟のサイン。皮と果肉の間に隙間ができて、実がパサパサになっている状態が目安です。
ナス科の野菜全般に共通して、枝につけたまま追熟させるのが、良質な種を得るための基本です。早熟収穫は避け、収穫最盛期に完熟した果実から採種するのがベストです。
実が大きく育った山本ナスや、完全に熟して腐敗が始まったヴィオレッタ・デ・フィレンツェのような実からも、たくさんの種子が採れたという事例もあります。腐敗している場合は揉み出すことで簡単に種が取り出せます。
2. 異品種との交雑に注意する
ナスは基本的に自家受粉しますが、10〜20%の割合で自然交雑が起こることがあります。異なる品種を同じ畑で育てる場合は、袋がけをするか、10m以上離して栽培すると、交雑を防ぎやすくなります。ひとつの畑で単一品種を育てると安心です。
ベランダなど昆虫が少ない場所では、人工授粉を行うと確実です。
3. 採種用の株を見極める
良い種を採るには、元気で病害虫に強い株を選ぶことが大切です。特に、以下のような特徴を持った株を選ぶと安心です:
- 草勢があり、枝ぶりが良い
- 品種の特徴(果形、大きさ、色)をしっかり表現している
- 採種果以外の収穫を止めると、養分が集中しやすくなる
成り疲れになる前の、草勢が充実している時期に採種果を着けるのが理想的です。採種果をつけた株は収穫量が減るため、収穫用と分けて管理すると効率的です。
採種果を1〜3個着けるだけで、500粒以上の種が採れることもあります。家庭用であれば1〜2株あれば十分です。
夏以降は水やりをしっかり行い、敷き藁などで乾燥を防ぐのもポイントです。
ナスの自家採種のやり方
ステップ1:揉み込む
追熟して柔らかくなった果実を手でしっかり揉み込みます。これにより種と果肉が分離しやすくなります。腐敗が進んでいる場合は、さらに種が取りやすくなります。
ステップ2:種を取り出す
ナスを水を張った容器の中で割り、果肉を指で崩して種を水中に揉み出します。果肉や皮のカスは取り除きましょう。一粒一粒丁寧に取り出す方法もあります。果実が硬い場合は少量の塩を加えると揉みやすくなります。
ステップ3:しっかりとすすぐ
水が透明になるまでしっかりとすすぎ洗いします。完熟した種は沈むので、浮いた果肉などを取り除きながら選別します。ザルを使うと流出防止になります。
ステップ4:乾燥させる
洗浄後は風通しの良い場所で天日干しし、その後新聞紙の上などでさらに日陰で3日程度乾燥させます。トレーなどに広げると風で飛ばされにくく便利です。
ステップ5:保管する
乾いた種子は茶封筒などに入れて種を保存します。封筒には品種名や採種日を記載しておくと便利です。保存は冷暗所が基本で、より長持ちさせたい場合は冷蔵庫での保存が効果的です。
ナスの種は嫌光性なので、遮光性の高い場所で保存するようにしましょう。湿気も大敵なので、湿潤を避けて冷所で管理するのがポイントです。
ナスの自家採種Q&A
Q. 黄色くなったナス、匂いが気になります。大丈夫?
A. 熟してくるとナス特有の香りが出てきますが、品質に問題はありません。
Q. 浮いている種子も使えますか?
A. 浮いた種子は未熟なことが多いので、沈んだものだけ使うのがベストです。
Q. 保存期間はどれくらい?
A. ナスの種は長命で、低温・乾燥状態を保てば4〜5年は高い発芽率を維持できます。ただし、春までは発芽率が低い「休眠期間」があるため、発芽試験は翌春に行うのが望ましいです。
Q. 発芽の適温は?
A. 発芽適温は25〜30℃、最低温度は15℃です。日中30℃・夜間20℃などの変温環境にすると、発芽が揃いやすくなります。生育には昼28〜32℃、夜18〜25℃が理想的です。
まとめ
ナスは、味も見た目もバリエーション豊かな野菜。固定種であれば、家庭菜園で種を採って毎年楽しむことができます。 育て方や採種方法を覚えれば、自分だけの種を次の世代につなげる楽しみも増えますよ。
ホームセンターなどで手に入る伝統品種のナスも、自家採種を重ねれば、土地に合ったナスへと育てていくことができます。