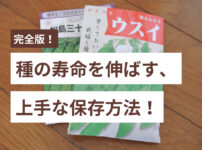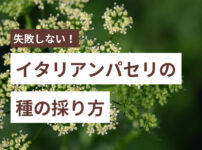「トウガラシの種ってどうやって採ればいいの?」「辛さで手が荒れないか心配…」そんな疑問を持っている方へ、今回はトウガラシの自家採種方法をご紹介します。
自分で育てたトウガラシから種を採ると、翌年も同じ品種を楽しむことができます。ちょっとしたコツを覚えるだけで、誰でも簡単に良い種が採れますよ。
トウガラシの種採りの概要
- 自家採種の時期:10月頃(霜が降りる前)
- 自家採種の方法:樹に付けたまま完熟させてから収穫
- 採れる種の量:1つの実から数十粒
- 自家採種に適した品種:万願寺とうがらし、鷹の爪、弥平とうがらし、カイエンペッパー
トウガラシの種採りのポイント
種はF1種ではなく固定種を!
種には「F1(エフワン)品種」と「固定種」があります。F1品種は、一代限りの交配によって作られた品種で、見た目や収穫量がそろいやすいという特徴がありますが、次の年に同じ性質の野菜ができるとは限りません。
一方、固定種や在来種は、代々同じ性質を受け継ぐので、自家採種に向いています。毎年安定したトウガラシを育てたいなら、最初から固定種を選ぶのが安心ですよ。
手袋・メガネでしっかりガード!
辛い成分(カプサイシン)は手や目に付くと大変です。種採りの作業をする際は必ず手袋をし、メガネやピンセットも活用すると安心です。
トウガラシの自家採種のやり方
1. 完熟まで枝につけておく
トウガラシは赤く色づいてからが完熟です。できるだけ長く枝につけたままにしておくことで、種がしっかり育ちます。
2. 実を切って種を取り出す
辛味成分があるので、手袋をして慎重に行いましょう。
万願寺唐辛子のような青いまま収穫する場合でも、完熟して赤くなってから収穫します。収穫後は軒下などの日陰で10日から2週間ほど追熟させ、果実の表面がしわしわになったら包丁で切って種を取り出します。白く丸い種子が見えたら、丁寧に取り分けましょう。
3. 水に浮かべて選別
水に浮いた種は空洞で発芽しないため、捨てます。沈んだ種を選びましょう。
4. 乾燥
取り出した種子は水洗いし、紙の上に広げて乾燥させます。風通しが良く、日が当たる場所で10日以上乾かし、夜は屋内に取り込みましょう。水気をしっかり取り、メッシュ袋やタオルで包んでおくのもおすすめです。
5. 保存
しっかり乾燥したら封筒などに入れ、さらに乾燥剤と一緒に缶に入れて冷蔵庫や冷暗所で種を保存します。
6. 発芽試験
翌年使う前に試しておくと安心です。
トウガラシの自家採種Q&A
Q. F1品種のトウガラシでも種は採れる?
A. 採ることはできますが、翌年に同じ形や辛さになるとは限りません。品質が安定しないため、自家採種には固定種をおすすめします。
Q. 水に浮いた種は使えませんか?
A. はい、基本的に中が空っぽで発芽しないので、浮いた種は捨てましょう。
Q. ピーマンと近くで育てると交雑しますか?
A. 同じ仲間なので、交雑の可能性があります。トウガラシの種を採りたい場合は、ピーマン類とは距離を離して育てましょう。
まとめ
トウガラシの自家採種は、完熟させることと乾燥をしっかりすることが大事です。作業時は辛味成分への対策も忘れずに。自分で採った種から育てたトウガラシは、育てる楽しみもひとしおですよ。
万願寺唐辛子や一味唐辛子づくり、さらには味噌作りと、収穫後の楽しみもどんどん広がるトウガラシ。ぜひ今年の秋は、自家採種にもチャレンジしてみてください!